宮島の鹿問題が世間に知れ渡るきっかけとなった2008年の新聞記事をご紹介します。
「宮島の鹿を救う人道支援の輪」という当時の給餌ボランティア団体が残してくれたブログに、新聞記事の全文が掲載されています。
 しかこ
しかこ当時の新聞記事を、ブログに残してもらえて感謝です
この新聞記事を読むことで、宮島の鹿問題の全体像が浮き彫りになってきます。
中国新聞 朝刊「広場」に掲載された悲痛な現実


まずは、2008年4月12日に中国新聞の朝刊「広場」に掲載された記事をご覧ください。
この「広場」は読者が投書できる欄で、投稿者さんは奈良の方だったそうです。
2008年4月12日 中国新聞朝刊「広場」
痛々しい宮島のシカ
先日、旅行会社のツアーに参加して宮島の厳島神社に参拝した。
さすがに日本三景の一つとうたわれ、世界遺産にも登録されている厳島神社は荘厳で美しく、すがすがしい気持ちで参拝させていただいた。
その後、清盛神社にも参拝しようと向かう途中、河原に小ジカを含めて二、三十頭のシカが足を投げ出して、頭までべったりと地面につけて、うつろな目をして寝ていた。
よく見ると、すべてのシカが非常にやせており、毛並みもまるで野良猫のように抜け落ちている。肌も出している部分もあり、痛々しく感じていたら、後ろから小学生の男の子が「あっ、あそこにシカが死んでいる」と叫びながら走ってきた。
いつも元気にはね回っている奈良公園のシカを見慣れている私には、一種異様な感じだった。参道には「シカに餌を与えないでください」との掲示が至る所にあり、地面はすべて石畳か砂利がひき詰められ、草も生えておらず、「神使」であるシカたちの餌は一体、なんだろうか。
これでは動物虐待ではないかと思いながら船に乗った。
投稿者さんが奈良の方ということで、奈良の鹿と比べて宮島の鹿の異常性に気づかれたようです。



僕たちのご先祖さんが、こんなことになっていたなんて..
鹿が非常にやせており、毛並みも悪く、肌も露出しているほど “ぼろぼろ” になっていた鹿たち。
子鹿を含めて20〜30頭が、頭まで地面につけてうつろな目をして寝ている(ぐったりしている)状況
だったようです。
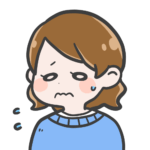
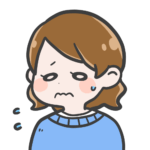
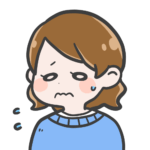
有名観光地にいる鹿たちがこんな状態だったなんて
投稿者さんが何時頃に宮島の市街地を訪れたのかはわかりませんが「ほとんどの鹿がうつろな目でぐったりしている」というのは異様な光景です。
通常、昼間であっても宮島の鹿は食べ物を探しているので、チャンスがあれば立ち上がり観光客にごはんをねだる光景をよく目にするからです。
産経新聞の記事に残る廿日市市の「駆除」方針


朝日新聞への投書から約1ヶ月後の2008年5月2日、産経新聞に衝撃的な記事が掲載されました。
なんと、宮島の鹿を「駆除」する方針が計画されていたというのです。
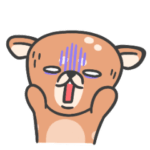
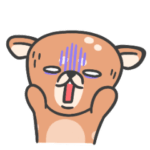
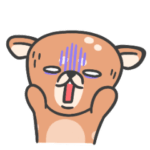
駆除・・・
2008年5月2日22時31分配信 産経新聞
「神の使い」は困りもの?宮島のシカ、増えすぎで対応困難
世界遺産の島・宮島で「神の使い」として大切にされながら、増えすぎてトラブルが絶えないニホンジカをめぐって、対応策が難航している。
過去の失敗例をもとに「駆除による頭数削減」を考える廿日市市に対し、広島県は「人間への依存性の改善」を要求。神聖な存在でかつ観光資源としても認知されるシカだけに、なかなか結論はでそうにない。
宮島に生息する野生のニホンジカは古来、「神鹿(しんろく)」として大切に扱われてきており、記念撮影の格好の被写体にもなる重要な観光資源。しかし、近年はエサを強引にもらおうとして観光客を追いかけ、ケガをさせるなど迷惑な行動も目立っている。また、ヤブツバキやリョウブなどの植物が食い荒らされる被害のほか、夏場はフン害も深刻化している。
シカへの対策については平成10年、合併前の旧宮島町がエサやりを防止してシカを山に帰し、本来の生態系の中で適正な頭数に戻す方針を決定。看板やパンフレットなどで「エサを与えないで」と呼びかてきたほか、動物園などシカの譲渡先を探していた時期もあったが、目立った効果はみられなかった。
しかし、その後もさらにシカ被害が増加。このため廿日市市は、旧宮島町時代の失敗を踏まえ、昨年(2007年)5月、有害鳥獣の計画的な駆除が可能になる「特定鳥獣保護管理計画」の対象地に宮島を加えるよう、広島県に要請。県は要請を受け、全島を対象にしたシカの生態に関する公的調査を初めて実施した。
その結果、約500頭のうち約200頭が、山ではなく厳島神社やフェリー乗り場周辺などに市街地に住み着いていることが判明。島の面積のわずか5%のエリアで、人家の周辺で観光客からのエサやゴミを食べて生きている実態が確認された。
こうした生態について県は、長年観光客や住民からエサを与えられてきたため-とし、「人間への依存状態を改善すればいい」と判断。また「神鹿として大切にされてきた存在。捕まえて殺すという方法はなじまない」という指摘もあったことから、今年3月、市に対し、駆除を視野に入れた「-計画」の対象とせず、市で対策を練るべき-との方針を伝えた。
この結論に、地元の廿日市市は「そうはいっても観光客らにエサを与えないよう周知徹底させるのが難しい。対策は10年前から練ってきたのだが…」と困惑しながらも、専門家や地元住民らも交えたシカ対策協議会を再び立ち上げ、改めて対策を検討することを決定。5月にも初会合を開く予定だが「有効な手立てがあるかどうか」と歯切れが悪く、シカの頭数削減への道は先行き不透明な情勢だ。
以上が、産経新聞に掲載された記事全文です。
この文章の中から、重要だと感じた部分を抜粋して解説していきます。
「駆除による頭数削減」を考える廿日市市
過去の失敗例をもとに「駆除による頭数削減」を考える廿日市市
まずここが、一番衝撃的な部分でした。
2008年当時、廿日市市は宮島の鹿を「駆除」して頭数を減らす方針だったようです。
今でこそ、表上は宮島の鹿を山に返して共存を図る、という主張をしていますが、当時は駆除による頭数削減を実行しようとしていたのです。



長年、神鹿と崇めてみんなで大切にしてきた鹿さんを、駆除なんて考えられない..
だとすると、
現在行なっている「山に鹿の餌が充分あるので給餌禁止を徹底すれば、自然に人と鹿の棲み分けがなされる」という主張と、大きく矛盾することになります
当時はそういう方針案も出たが、共存に舵を切った。
ということは考えずらいです。
大昔から「神鹿(しんろく)」として大切にされてきた宮島のシンボルでもある鹿を、いきなり「駆除する」という発想になることは不自然に感じます。
廿日市市は山に鹿の餌資源がわずかであることを認識していて、共存という方向性が時間も労力もかかり手間であると判断したのではないでしょうか。
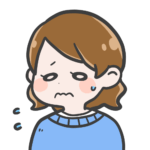
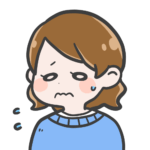
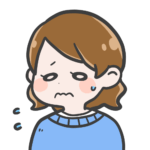
人間の都合で鹿さんを振り回しているのね・・
この事実から、
鹿と自然に共存することが難しい = 山に鹿の餌資源が不足している
という構図が見えてきます。


この葉っぱは鹿が食べられないアメリカシキミ(撮影:25.5.11 大元公園)
一見すると、鹿にとっても緑豊かな食べ物に困らない場所に見えるのが宮島です。
ですが、宮島は瀬戸内海の他の島とも違い、春や夏でも葛の葉、竹、笹が生えません。
逆に写真のような
- シキミ
- シダ
- サカキ
- アセビ
などの、鹿が食べられない植物がたくさん自生しています。
宮島は土壌の塩分濃度が高く、もともと鹿の餌資源が不足した島であるにも関わらず、人間が鹿を観光利用して増やしたため、鹿の食べられる植物がさらに生えにくい環境下になったのです。
旧宮島町は平成10年(1998年)にエサやり防止の方針


平成10年、合併前の旧宮島町がエサやりを防止してシカを山に帰し、本来の生態系の中で適正な頭数に戻す方針を決定
平成10年(1998年)から旧宮島町ではエサやりを防止して山に帰す、という方針を打ち出していました。
廿日市市に合併した際に、山に鹿の餌が豊富にあるのなら、この計画を引き継げばそれで済む話だったはずです。



山に餌が足りないから町にでるんだけど
鹿は、夜になると山に寝に帰りますが、餌資源がわずかな宮島では、昼になると餌を求めてまた市街地にやってきます
宮島町時代は、まさか神鹿を駆除しようだなんて考えていなかったでしょう。
ですが2005年(平成17年)に旧宮島町が廿日市市に合併してから、宮島の鹿対策の決定権を廿日市市が持つことになったのです。
そして、廿日市市は堂々と「駆除」という方針を打ち出したのです。
廿日市市は宮島を「特定有害鳥獣保護管理計画」の対象地に


昨年5月(2007年)、有害鳥獣の計画的な駆除が可能になる「特定鳥獣保護管理計画」の対象地に宮島を加えるよう、(廿日市市は)広島県に要請
廿日市市は宮島の鹿の「駆除」を可能にするために、「特定有害鳥獣保護管理計画」の対象地に宮島を加えるよう広島県に要請しました。
そして、実際に宮島は「特定有害鳥獣保護管理計画」の対象地となったのです。



表上は駆除するためにとは、
絶対に言わなかったんでしょうね
ただ、駆除するという方針に関しては広島県が許可を出しませんでした。それが分かるのが以下の一文です。
「神鹿として大切にされてきた存在。捕まえて殺すという方法はなじまない」という指摘もあったことから、今年3月、市に対し、駆除を視野に入れた「-計画」の対象とせず、市で対策を練るべき-との方針を伝えた
「神鹿として大切にされてきた存在。捕まえて殺すという方法はなじまない」ということで、広島県は廿日市市の駆除計画を跳ね返し、別の対策を講じるように伝えています。



助かった・・・
そうした経緯を経て作られたのが、宮島地域シカ保護管理計画なのです。
まとめ


2008年の産経新聞の記事は、現在の宮島の鹿問題を考える上でとても貴重な情報です。
廿日市市が宮島の鹿の「駆除」を検討していたということは、山に鹿の餌資源が不足していることを認識していたのでしょう。
神鹿(しんろく)として鹿を長年観光地のシンボルとして利用させてもらったお陰で、宮島は世界でも有名な観光地になりました。
ですが、
その立役者である鹿を、廿日市市は「駆除」しようとしていたのです
これは、とても恐ろしいことです。
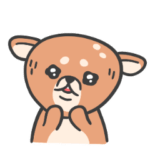
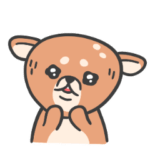
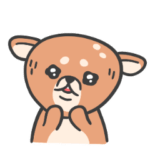
人間さんはなんで
私たちを大切にしてくれないの
廿日市市は、実際に「駆除」を行うことはありませんでしたが、それは広島県が許可を出さなかったからであり、もし広島県が許可していたら宮島の鹿を駆除していたのです。
また、
宮島を「特定鳥獣保護管理計画」の対象地に含めたのは、宮島の鹿を「駆除」するためでもありました
鹿を「駆除」して減らそうとしていた廿日市市。
現在の宮島地域シカ保護管理計画が、本当に鹿との共存を目指しているものなのか、私たちは今一度立ち止まって考える必要があります。
山に鹿の餌資源がないと分かっていて「給餌禁止のお願い」をすることは、間接的に鹿を餓死させ削減させる計画なのでは、と疑われても仕方がないでしょう
まずは一部のボランティアによる給餌活動だけでも、認めるところから始めてみてはどうでしょうか。



まずは一部の給餌活動を公認にして、
皆で一緒に助け合って行けたら良いね
この給餌活動の恩恵を、廿日市市も、広島県もたくさん受けているはずです。
現在の廿日市市の方針を支持している方もおられますが、それははたして真実なのでしょうか。他の記事もご覧になり、深く考えて頂きたいです。


